アナ・プタック
AIRと私:スケールの活動──日本へのアーティスティック・フィールド・トリップの報告
1) AIRプログラムのキュレーター
私の通常の仕事はレジデンシーを企画運営することである。ここ数年は、ワルシャワに数カ月間滞在することを決めたアーティストたちのサポートに携わっている。アーティストが滞在を決断する理由は、一般的に以下の三つの動機のうちのひとつだろう。第一に、アーティストのなかには特定の芸術活動に取り組むために A-I-Rラボラトリーのプログラムへの参加招待を希望している人たちがいる。彼らは作品制作にあたり自分のコンセプトの実現を支援してくれる機関を探しており、そうした彼らの希望に沿うのがA-I-Rのプログラムなのだ。第二に、芸術研究を目的とするアーティストもいる。彼らの研究からは新たな成果が生まれるかもしれない。しかし、私たちのプログラムが基本的に前提としているのは、この「かもしれない」がまさに「かもしれない」という可能性であって、「そうでなければならない」という強制ではない。こうした研究では、ワルシャワで確認された社会現象、ワルシャワの歴史、ワルシャワを構成しているユニークな関係の集積、さらにはワルシャワの建築、経済、政治的な構成が分析され、マッピングされる。ワルシャワのアーカイブが貸し出され、テーマを絞った話し合いが住民や機関を相手に行なわれる。第三に、自分の時間を取り戻すためにA-I-Rラボラトリーにやってくる人々もいる。日常的な責任というプレッシャーから逃れ、創造的な実験を行ないたいという希望を抱いてやってくるのである。
私たちA-I-Rラボラトリーのキュレーターは、アーティストが抱く疑問や期待と、ワルシャワという都市そのもの、およびワルシャワ在住の専門家に関して私たちが持っている情報がもたらす可能性とのあいだを仲介する役割を担っている。ワルシャワ在住の専門家とは、研究者やワルシャワでの日々の生活や仕事を通して培われた知識を持つ人々のことである。つまるところアーティストは知識を探し伝えるプロセスを脚色し美化し、それらを芸術的解釈にゆだねる。ギャラリー以外での展覧会やイベントといったかたちで開催される頻度が高まりつつあるこの概念的な芸術活動の要素も、ワルシャワのA-I-Rラボラトリーがサポートする芸術的、学芸的ワークの重要な特徴となっている。

左=A-I-Rラボラトリーでのレジデンス風景。ウジャドゥスキー城現代美術センターのスタッフがセンターの前で種まきをしている。アーティストのキッチンガーデンをつくることがプロジェクトの一部分となっている。ジュリエット・デルベンサルとパヴェル・クラックによる作品《私たちは庭のようだ》(2012)
右=アーティストたちがモバイル彫刻の水陸両用車に乗船してヴィスワ川を下る試み(この試みは成功した)。2012年にA-I-Rラボラトリーに滞在したフランシス・ソーバーンの作品?
ともに撮影=マグダレナ・スタロヴェイスカ
A-I-Rラボラトリーとアーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]とのコラボレーションのアイディアは、レジデンシー企画団体の世界的ネットワークであるレズ・アルティスが主宰した会議の話し合いのなかから生まれた。会議は現代文化の具体的な作品であり、アーティストやアーティストの作業の可動性をかつてないほど効率的にするサポートをしている。会議ではどのセッションにも、小規模団体、一人で運営している活動、また国の機関にいたるまで多様な形態の組織の代表者たちが何十人、ときには何百人も集まった。クリエイティブなレジデンシー実施団体が集まって独自の協会を設立し、自らを独立系機関だとみなすフォーラムを設けたという事実は、まさに広範囲にわたるニーズがある証拠である。しかし、この共通した標準化へのニーズと努力にもかかわらず、プログラムの企画方法や提携するパートナー施設同士の関係は、いまだに個人レベルでの交流や、双方が根差した芸術世界以外の共有価値観に基づいた相互信頼の構築、どこまでオープンにするのかを決定する地政学的要素、芸術的交流が向かうだろう方向性に著しく依拠している。?
A-I-Rラボラトリーのディレクター、イカ・シェンキェビチ・ノワスカ氏とAITの塩見有子氏はレジデンシー・プログラムに対して多くの共通した認識を持っていた。個別化され、アーティストのニーズを取り入れたレジデンシーの運営方式を二人とも前提としており、組織の財政面かつ組織面での安定性と、柔軟で中規模のプログラムを実現させるための努力とのあいだでバランスを取っている。また、双方ともこのレジデンシー組織を、展覧会で展示する完成「作品」や、レジデンシーから生まれるプロジェクトという形式の獲得を目的にすることではなく、芸術活動における研究と実験のプロセスだととらえている。最終的には、世代的な経験をある種共有しているという認識が大きな意味を持っていたことは明らかだ。A-I-RラボラトリーもAITも十数年にわたる活動実績があり、双方のディレクターが個人的に結びつき、アートのためのレジデンシー運営に独自の形式を作り上げ発展させてきた。
ワルシャワの場合、ウジャドゥスキー城現代美術センターという大規模な国際展示センターの枠組み内でユニットを設立する形式を採っている。ウジャドゥスキー城現代美術センターはA-I-Rラボラトリーの親組織である。しかし東京のAITは、現代アートについてのアイディア交換、教育、批評のためのディスコースの場をつくることを目的に、6名のキュレーター、オーガナイザーが補足的なツールとして設立したものである。ワルシャワでも東京でも、レジデンシー・プログラムは芸術活動を計画する方法となっており、展覧会の代わりになるもの、展覧会を補完するものになっている。このような考えで私たちは一連のレジデンシーの紹介・運営を行なっている。2014年に始まるサイクルでは、ポーランドと日本のアーティストを対象にレジデンシー・プログラムが紹介されるだろう。?
私自身はこれまでレジデンシーに参加した経験はなかった。それゆえAITから招かれたフィールドトリップはレジデンシーの意義とそれが何をもたらすのかを知る機会であった。また私の研究と調査にこの上なく重要であったトピックのひとつをかたちにするという目的もある。さまざまな世代のアーティストと関わりながら、知識交換のプロセスが短期間、長期間のコミュニティを生み出す様子を目にすることができた。思考、疑問、回答の流れの本質が相互教育であるならば、それは実際のところ知識の直線的な流れや蓄積を経由するのではなく、小規模、大規模の社会的集団を通して起こる。概念的な芸術表現の言語に関心を持っているアーティスト、キュレーター、オーガナイザーらが東京やその他の場所でどのように組織を運営し、どのように一般の人々を定義し、どのように一般の人々と本質的なテーマについて話し合っているのか。私の興味はそれらを探ることにあった。
2)キュレーター・イン・レジデンス
では、レジデンス・キュレーターの仕事とは何だろう。それは地域に根差した芸術活動や地元の施設、そこで行なわれる議論を詳しく知ることだ。しかしレジデンス・キュレーターであるということは、その都市の中に迷い込むことでもある。スタジオ訪問の際は頻繁に遅刻し、無作法をしでかし、大切なイベントを見逃す。その際、言葉がわからないことを理由にして詫びる。この異邦人感も都市を理解するためのツールである。ある意味、私の東京をめぐる旅はワルシャワでの自分の仕事の鏡像と対峙することから始まった。しかし今回は、「新規」に始めるという恩恵を受ける側であった。AITでアーティスト・イン・レジデンスを担当しているキュレーター堀内奈穂子氏は、アートを変えよう(Making Art Different[MAD])プログラム運営者の一人でもある。MADは独立系教育機関であり、キュレーター業務の研究、芸術、国際アート研究の夜間コースを提供している。私が奈穂子と知り合ったのは、彼女が数日間ワルシャワに滞在したときのことだ。そのとき、私たちはお互いに興味を持つ領域について語り合うことができ、それにより彼女のアドバイスに沿うこともできた。私の日本滞在は特定の展覧会やフェスティバルの企画に絡んだものではなかったので、スタジオ訪問や「素顔」のアーティストとの対談した際は、自然でリラックスした会話をすることができた。こうした自然な会話のなかからアーティストの作品が徐々に浮き彫りになる。コミュニケーションのプロセスでは、言葉の複雑さ、旅行、都市、さらには面会場所、そこにたどり着くまでの困難さ、目的地を見つける難しさが熱心に語られた。私の疑問や質問と言えば──東京にはどれくらいアンダーグラウンドの文化があるのだろう? アーティストたちは社会のなかで、あるいはアーティストのコミュニティのなかで、自分たちの居場所をどのようにとらえているのだろう? 国民的論議のレベルではどのようにとらえられているのだろう? 3月11日の地震や津波のようなトラウマ的惨事と、それに続いて発生した政府の安全対策への信頼危機の後に、アート系機関やアート活動の本質について検討がされたのだろうか? 参加の感情はどのように表現されるのか? 懸念だろうか、ユーモアだろうか、それとも不信だろうか? いまでは非常に大胆に聞こえるこうした質問の根底には、個人、そして個人的な活動歴に対する興味があった。
AITが用意してくれたレジデント・プログラムのおかげで私の置かれた環境はとても贅沢なものであった。なによりも、私自身と時間との付き合い方が変わるという点が贅沢であった。私がミーティングを開こうとしたときにしばしば耳にしたのは、「あなたはとてもお忙しいでしょう?」という丁重な言葉だった。相手が私を尊重していることを示す丁寧な表現だ。それは私の時間に対する尊重、昼も夜も長時間働いていることに対する尊重である。ミーティングを開くことができるのかどうかを尋ねる言葉でもあり、ときには生じている文化的な誤解が否定によって克服されることを切に求めているようでさえあった。「いえいえ、私は忙しくありませんよ。ぜひお話しましょう」

暗渠が明渠になる東京の珍しい場所
3) 組織の景色
最初の1週間、私はおもに歩くことに費やした。何時間も歩き、自分なりに都市の地図を作成した。私の教会(conbento)、お気に入りのスープ、効率よく買い物に行く方法などを書き込んだ地図だ。またワルシャワでの仕事はひとまず片づけ、心の中に思い描いていた日本のアートと、それがどこでどうやって発見できるのかを結びつける新しいネットワークをゆっくりと作り上げることに取り組んだ。こうした探索の初期に特に夢中になったのは、企業ミュージアムである。創業者の記念館もあれば、企業の製品が形而上学的に構成されているミュージアムもあった。こうした企業ミュージアムは企業ブランドの象徴的なメッセージをはっきりと強調している一方、その企業の製品に対する好感を育む一助にもなっている。ミュージアムは美しく展示品をレイアウトしており、ほとんどが小規模だ。公立ミュージアムの大規模なコレクションを補完する素晴らしいミュージアムだと思う。企業ミュージアムは各企業のビジネスに関連した展示をしているので、展示には物語もある。それは展示して見せたいという動きと、見せるのをためらうという抑制する動きが絡まっているということを物質的に表現するのと同時に、ものについての物語であり、さらに会社の伝統、ないしはコレクターの情熱についての物語にほかならない。仕事は終わり、残っているのは美しく、いまや使用されなくなったもの。製品達成までの努力、製品が使用されるコンテクスト、製品の展示へとつながる多様な社会的経済的メッセージは、ミュージアムの展示では表わしきれない。
21_21 DESIGN SIGHTが開催した「日本のデザインミュージアム実現にむけて展(Toward a DESIGN MUSEUM JAPAN)」紹介のなかで、オーガナイザーたちはこうした建築、製紙、製皮、化粧品、パン工場などの企業ミュージアムについて言及している。企業ミュージアムの中に大きな将来のミュージアムの核心を見ているのである。私がインスピレーションを受けたのは、こうしたミュージアムが設立された土地の歴史と、さまざまに異なる集団の人々を結びつける材料に関する知識を伝達するものとしての商品製造にそれほど関係していないデザイン面との関係の観点から展示を考えることである。企業が成長を遂げていった歴史における特定の節目と深く関わっている記念館もまた、地震が多い大地の上で営まれてきたミュージアム技術の歴史なのである。私が気に入ったミュージアムのひとつが、荏原製作所の創業者、畠山一清が1964年に設立した畠山記念館であった。ここで私はわびの美意識を反映した茶道具、詩形式の旅先からの手紙、展示も保管も移動もできるように装丁された掛け軸を鑑賞した。私は荏原製作所がつくった巨大な濾過機、穴あけ機、ポンプなど、この展示では見ることはできないものを頭に浮かべ、それらが中規模の地震対策として、ガラスのショーケースの展示物のようにプラスティックのワイヤーで固定された繊細な展示物とつながっているところを想像した。そして盛んに鑑賞するよう勧められた場所は、白金台の脇道にひっそりと佇む庭のある日本化された国際様式の建物だ。そこではモダニストの展示方式が日本の家屋の伝統的建築法と自由に、そして自然なかたちで混在している。

東京探検。東京の道案内板
典型化された日本の風景のなかで、個々の場所は小規模な都会的中心地で占められているようかのようだ。こうした中心地は数多くある。このような中心地のなかで、現代アートがその土地のコミュニティと付き合いながら活動している。その多くは東京にあるが、東京郊外の街で活動をしている人々と知り合う機会もあった。彼らに会って心を動かされたのは、いずれの場合も、コミュニティとの「付き合い」が抽象的な意味を持つものではまったくなく、スタッフ、ゲスト、コラボレーティング・アーティスト、支援している当局者やボランティアが実際に作業に貢献していることだった。私はアート施設自立のための財政的、政治的資源についてのディスカッションに参加した。このディスカッションはアーカスプロジェクトが茨城県守谷市で主催したものだ。小学校の跡地を利用したアーカスプロジェクトのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムには3名の海外アーティストが参加しており、そのスタジオ開放日のイベントの一環として行なわれた。東京からも招待客、アーティスト、キュレーター、批評家たちが参加した。だが、なによりもはっきりしていたのは、このイベントが非常に地元に根付いたものであったことだ。
三人のアーティスト、ロドリゴ・ゴンザレス・カスティージョ、シビレ・ノイマイヤー、ナンデシャ・シャンティ・プラカシュが三カ月のレジデンシーの成果のプレゼンテーションを行なった。プレゼンテーションのメインは、アーティストと守谷市やその周辺の住民とが知識伝達に関して一連のやり取りをしてきたことを明らかにすることであり、それをさまざまなメディアを利用して翻訳することだった。ゴンザレス・カスティージョは、彼独自の手法と、日本の豊かな伝統から抽出したシンプルでアナログな印刷技術を用い、視覚的イメージを持ち寄る市民とワークショップを営み版画をつくるアーティストとのあいだで一種の物々交換、交流を行なった。ノイマイヤーは革新的で詩的なショートカットを披露した。彼女の情動的な作品を構成していたのは、床にばらまかれた土の匂いが充満した黒い空間と、耕作用に乾燥された土が輪の形に投げつけられるリズムに脈動するビデオのスクリーンであった。一方では周囲を取り囲む茨城の農地があり、もう一方には土壌の放射能汚染により生み出された危機があり、これら二つがこの作品のなかに疑いようもなくはっきりとした文脈を形成していた。しかし、こうした両極のあいだには、人々が訪れ、会話が交わされたという全ネットワークが存在している。作品は、このネットワークから形作られたのである。
組織としてのアーカスは地方自治体と協力しており、双方ともその関係を維持するためさまざまな活動を行なっている。このイベントに参加した市民はアーティストの作品のなかで自分たちを認識する機会があった。これは自然に起こる類の現象ではなく、取り組み発展させていくものである。しかし私が感動したのは、アーカスが組織としてオープンであることだ。スタジオの開放日、幼い児童たちが見学にやってきた。この見学で児童たちは、徹底的に磨き上げられてミュージアムのどこかに展示される完成作品ではなく、アートがつくられる「キッチン」を観る機会があった。イベントが進行するなか、私は地元の議員に会った。彼は、アーカスのための資金を自治体の予算から融通するよう働きかけを行なっている人の一人だ。どちらかと言えば退屈で単調な伝統芸術とは異なり、現代アートは現実世界では探しても見つからない見地から物事を見ることを可能にし、新しい何かを見ることを可能にすると彼は言う。ちなみに彼は技術者であり、正式に芸術を学んだ経験はない。

元教室。2013年にアーカスに滞在したナンデシャ・シャンティ・プラカシュのオープン・スタジオの風景
取手アートプロジェクト(TAP)もまたユニークな環境と状況のなかでアートの活動拠点を設置するという興味深い可能性を提示している。ここも東京の外に位置し、東京のベッドタウンでありながら、ヨーロッパの基準からすれば巨大な都市である。TAPは仲介役として、アートと展覧会の結びつきを促進するイベントを企画している。東京芸術大学構内にあり、現役の大学生と地元の住民が参加している。TAPのオフィスはボランティアにより運営されており、TAPやTAPとのコラボレーションにより開始・実施される公式、非公式の取り組みは、コンペティション企画から、地元の特性を活かしたプロジェクトのためにアーティストに制作スタジオを提供するなど多岐にわたっている。そのなかのひとつが長期プロジェクト「半農半芸」である。これはアーティストである岩間賢氏が食の生産と交換、食の生産についての教育の場として始めたものである。ここでもまた、2011年の大震災によりプロジェクトの目的と運営方法を作り直す必要性が生じた。借りていた農地は放射能で汚染されており、新たな活動はその農地の除染作業から始まった。プロジェクトはいま、地元産食材を販売するマーケットを開いている。

取手市にあるアーティスト・イニシアティブによるスタジオなどを訪問
私はまた、広島県尾道市にある周辺環境とコミュニティを結びつける別の取り組みを偶然知ることになった。私は瀬戸内海に浮かぶ小島、百島の近くで滞在できる場所を探していたのだった。この島でも、柳幸典氏が毎年招へいするアーティストたちによりさまざまな活動が行なわれている。柳氏のスタジオは現在廃校となっている小学校だ。冬が訪れる前にアーティストたちが退去した島には冷たい冬の風が吹いていた。尾道に戻るフェリーを待っているあいだ、私は農家が箱詰めされたみかんを裁断機に積んでいる様子や、もはや農業では生活できなくなり島外で働いている住民たちがフェリーから下船し、家路につく様子を見ていた。観光シーズンは終わり、辺り一面が脆弱な側面──厳しい生活環境、島の孤立、海水の中で錆びついている鉄の構造物、農業と漁業に基づいた生活に代わる方法を創出しようとした努力を雄弁に語る産業の遺物──を露わにしていた。
私が滞在したのはゲストハウス「あなごのねどこ」である。商店街の中にあるその民宿の外観は簡単に見落とされてしまうが、伝統的な宿屋の驚くべき空間が内側に広がっている。フロントにある小さなカフェスペースでスライドを用いたトークセッションが行なわれた。私には理解できない手書きの日本語を眺めながら、私は懐かしい場所やもの──湖上の小島にあるアルメリア教会、アララト・ブランデーの瓶の形、イエレバン周辺の茫漠たる原野の風景──を思い出し始めていた。地元大学の講師で建築家の渡邉義孝氏が旅の経験の大切さ、建築家としての仕事についてのプレゼンテーションを行なっていたようだ。また「あなごのねどこ」は、地元住民の努力のおかげで急進的で破壊的な建物の現代化の波から救われた尾道市の町屋のひとつであることもわかった。?
日本の伝統家屋を守ろうという住民グループは、同じく再生された町屋で文化・公共活動をしている何人かの人々を引き寄せた。尾道出身のアーティスト、小野環氏は毎年そうした伝統家屋のひとつで開催するAIR尾道に海外からのアーティストを招いている。「あなごのねどこ」のオーナー、豊田雅子氏は文化的イベントに場所を提供し、地元住民や旅行者の交流の場としてのゲストハウスを経営している。冬場に欠かせない炬燵は、暖房がない昔ながらの日本家屋、そして同じ炬燵に当たる人達と暖かな炬燵布団の下でお互いの脚がぶつかりあいながら交わす会話にとって、このうえなく実用的な解決方法となることがわかった。
地元の人々による活性化の取り組みのなか、関係者は協力して働き、外部から招かれたゲストたちは地元グループの関心や懸念、好奇心に注目しつつコラボレーション活動を強化している。しかし、こうした場やコミュニティには連続性や記憶がある。それは欠くことのできない部分であり、絶えず移動している人々の提案の代わりになるものであり、芸術的な試みから流れ出るエネルギーを理性的に使用することをうながすものである。私が上記で述べてきた場所は、ある程度、現代のビジュアル・アート、パフォーマンス・アートの批評的活動に対してオープンな姿勢を明らかに示しながらも、地方組織の昔ながらのモデルを設けている。同様に、アーティストたちも社会的状況との関係は絶たないが、文化形式の循環状況に基づいたパフォーマンスや実演に携わることを好み、新しい現実の表現形を放棄することがよくある。

尾道市の「あなごのねどこ」での旅行に関するレクチャー風景
最後に、相関関係的な活動を考えるにあたり、私の指標でありインスピレーションとなった二つの施設について触れておきたい。公的機関との関係や活動規模の面ではどちらかを選択しようにも比較はできない。それでも、アートを発表する伝統的な場について考える際の重要な柱だと思われる。というのもこれらの施設は、独立というコンセプトではなく、アート活動と、そうした活動が行なわれる社会、財政、政治的背景とのあいだの相互関係のあり方を検討することに重点を置いているからだ。
ひとつは仙台市にあるせんだいメディアテークだ。ここは芸術性のあるドキュメントなどの制作、保管、展示を専門に扱う施設である。そうしたドキュメントのクリエイターはプロの作家だったり、締切日が設けられていない審査に応募したり、メディアテークのチームが制作中の記録作品シリーズに参加している個人やグループだったりする。この立派な公立図書館は、六階建ての建物の中にある。伊東豊雄氏が設計したこの建物の主な特徴は透明性だ。建物全面がガラス張りであり、周囲の状況が変わるにつれて屋外の形状、色彩が映し出される。
この施設を知るまでは、個人宅であれ、施設であれ、バーであれ、日本の通りに並ぶ内側の見えない建物への近づきにくさを定義することは難しかったかもしれない。大方の場合、内側がオープンになっているのは都市のなかの昔ながらの一画にあるクラフト・ワークショップだけであり、そうした意味から言えば、メディアテークは一種のワークショップとなっており、施設が発信する情報やイメージにアクセスする場を創り出している。メディアティークには早朝からあらゆる年代の人々であふれている。特に重要なのは、騒々しくせわしない公共空間では通常あまり見かけない高齢者が数多くいることだ。たくさんの人々が図書館を利用していたが、なかには寝転んで本を読んだり、おしゃべりに興じたり、冬の陽だまりのなかで日向ぼっこをしたり、建物内のあちこちに置いてあるマットや肘掛け椅子でリラックスする利用者の姿があった。
メディアテークはまた現代芸術の施設でもあり、そのアーカイブからはアート関連を含めさまざまな文書や作品にアクセスできる。このアーカイブのおかげで、私はダムタイプの過去の作品を見ることができた。現代の危機の形を内省的に考えていた私にとって、ダムタイプのアートは新たな疑問を生んだ。それは、自らを一枚岩と見なす社会に対し、どれだけ多くの種類の愛のかたちが敗北し失われていることだろうという疑問だ。独立系メディアの経験豊富なクリエイター、甲斐賢治氏と清水チナツ氏共同監修のもとでメディアテークにより保存されているメディア・社会アーカイブの目的は、地元や世界の情報が疑う余地のないものとして提供されないようにすることだ。メディアテークのプロジェクトのひとつは、私にとってたいへん重要な意味を持つものであった。それは3月11日のアーカイブである。インターネットでも見ることができ、継続的に追加されているこのアーカイブには、東北地方を襲った地震と津波の被災地の人々の話が記録されている。これには英語の字幕もついている。

せんだいメディアテークの内と外
一方のhanare×Social Kitchen(ハナレ×ソーシャル・キッチン)は、hanareが京都に設立した小規模な施設であり活動の場である。そこには作業場、アート関連活動などの活動場所、持続可能な食の生産の原則に則った健康的なメニューを提供する小さなカフェもある。低層の一軒家が並ぶ地区の、寺院と学校、隣家の壁に囲まれた建物の中にある。しかしhanareが力を注いでいるのは、牧歌的な周辺の自然の育成や生態系に配慮した消費に基づいたアプローチの保護ではなく、アートや現代の社会政治的な課題を扱う手順のなかに個人的な取り組みの要素を導入することであり、独自のワークや活動によってセンターを運営している。そこでは意見の一致がけっして目標ではない。
ソーシャル・キッチンはオーナーたちの発案による活動をサポートするベースとなっているが、「よりよい市民」になろうという努力と、現実に対する批判的な態度を自らのなかで両立させている人々にも開放されている。そのため、この施設では地方選挙をめぐる議論の一環として重要なトピックを話し合うために設立された地域委員会の会議や、東日本大震災の社会政治的な影響に取り組み、地震による福島第一原子力発電所の損壊がもたらした結果についての情報を分析するワーキンググループ活動などが行なわれている。アーティストとの活動にもプロセス重視で実験的な要素があり、ワン・イヤー・オブ・エクスポラレーション(One Year of Exploration)という方式で実施されている。この方式では、アーティストたちは彼らの活動にあったリズムで一般の人々と触れる空間が与えられる。

ハナレ×ソーシャル・キッチンのカフェ
4)キュレーター・イン・レジデント
素晴らしいミュージアム、民間のギャラリー、商業施設、独立のために奮闘している人々、おたく文化から伝統芸術の養成まである東京のアートシーンには、あらゆる種類のアートの姿勢や展示の戦略を発見する膨大で無限の可能性がある。しかしレジデンシーの本質と真の喜びは、成果のレビューや参加者の選出、一度のミーティングに限らず、コミュニケーションとウォーキング活動のために何回もミーティングを行なう方法を超えた可能性、つまり、リストに並べられた計画の項目を成し遂げるのではなく、偶然生じる状況にこそあるのだ。各地を移動するキュレーターが異なる場所でプロジェクトや展覧会を企画するよう招かれるプログラムは数多くある一方、スケジュールの枠を超えるための、そして知識を得る一連の思考・方法と独創性のない方法とのあいだの不協和音を体験するための時間も場所もないことはよくある。
施設はどこからともなく現われるものではない。施設は人々によって運営されるものである。組織的、個人的要素の双方が芸術活動が地元に根付く方法を決め、どのように地域を超えた範囲と意義が実体化されるのかを決めるのである。数年前のレジデンシー企画団体のなかでは、芸術活動を目的達成のための道具として利用することに対する恐れがまだ優勢であった。言い換えれば、アートが社会に与えるだろうと予想される影響という手段によってであれ、あるいはスポンサーの前に並べることができる「作品」を所有する義務によってであれ、あるいは文化外交のトップダウンの前提に適合するようにアーティストのレジデンシーを形成することによってであれ、地域コミュニティの利益になるように活動することにより、レジデンシーを運営する目的を正当化させる必要性に対する恐れである。こうした問題はいまだなくなっていない。レジデンシー企画団体が感じている問題の大きさは、他の芸術世界よりも明らかにあるポイントを強調していることから生じているのだろう。そのポイントとは、アート作品を含めた現代作品の本質が、可動性や柔軟な作業時間の点において、また周辺環境とのつながりに欠け、同時に自己中心的な運営をしながらの地域の環境や状況への順応性といった点において、グローバル資本主義にマッチしているということだ。
しかし、私がここで簡単に紹介した施設が示しているように、まさにレジデンシー・センターを通すことにより(もちろんこうしたセンターだけを通すのではないし、外国人アーティストの移動手段としては必ずしも「滞在」でなくてもいいが)、作業としてのアート活動に戻り、その一時的かつ移動可能な成果を一定のコミュニティに結びけることは可能だと思われる。レジデンシーはそれ自体で、あるいはその前提において、非物質的な作品を通して資金を集めるという論理に対抗した救済策として論じることはできない。ガル・キルム★1は、具体的な恩恵は芸術活動が行なわれる「空間化(spatialisation)」から引き出されうると仮定した作家の一人であり、レジデンシー組織の制度化を使ってその点を説明している。ヨーロッパでは、レジデンシー・センターを運営するコストが合法的占拠にかかるコストに取って代わり、空家となったスペースが不正規の人々(例えば移民など合法的に居住場所を得ることができない人々は言うまでもなく)により違法に占拠される事態を防いでいる。パスカル・ギーレン★2はアート界で新自由主義的な文化の生産を行なっているラボラトリーの分析、歴史的調査を行なっている。移動が生み出した、この類のレジデント・アーティストやキュレーターを私たちは間違いなく簡単にリストアップすることができるだろう。彼らはレジデンシー・プログラムを掲載したギーレンの長いリストに自らの時間と実験の場をいつでも柔軟に当てはめることができ、世界についてもっともらしいコメントをしている。レジデンシー・センターの人気がまさに高まっているということは、アーティストのクリエイティヴ活動の発表の場を提供する方法が模索されている証拠かもしれないし、芸術制作にかかる時間とコストの管理、およびそこに含まれるある種の知識が管理できるように活動の発表の場を空間化する方法が模索されている証拠かもしれない。
しかし、アート施設の機能方法に対する批判も、新自由主義的でグローバルな作品モデル(この場合文化的なモデル)におけるポスト・コンセプチュアルで批評的アートの混乱も、芸術活動が自発的に目的を達成することを可能にする組織や自己組織のためのモデルを探す権利をわれわれから奪うことはない。ここでは、こういったモデルを探すためにどのような目的を選択するかは、他のモデルと同様、あらかじめ決まってくるものだろう。そしてまたしても、ここでの懸念は、社会的文脈から芸術活動を切り離すという意味での自主性にあるのではなく、創作活動を行なう組織に原因性を持たせることにある。ギーレンはそのような代替の領域を、さまざまなアートイベントがあるなかで、密接性や不活発性を特徴とする諸活動のなかに求めている。同様に、キルムが示したようなアナーキスト的な観点から言えば、不法占拠や不法侵入は、有意義で合理的なアートのコミュニケーションの循環を生み出すことを可能にする一種のツールかもしれない。私の考えるところ、重要なのは実行される活動の規模であり、また仕事場を創出し、クリエイティブな作品を発表する人々のグループにコミュニケーション手段を順応させることができるかどうかである。
さまざまな制度の形式や文化政策に精通することから生じる経験は、アートのコミュニケーションの可能性を普及させるという希望をもたらす。不活発性も緊密性も日本の施設の組織運営方針の性格に備わっているものではないように思えるかもしれない。だがその一方で、アーティストが自分の国を代表することや、施設が後援者機関や団体を代表する表現形式といった枠を超えることにより、アーティストやオーガナイザーたちのアイディアの多様性や価値が評価できるようになるのである。

左=のんびり旅。石巻に向かう途中の車窓/右=誰が話しているの? 百島にて
以上、特記なきもの撮影=アナ・プタック
AITのレジデンシーに対する考え方のおかげで、私は従来のアート調査のやり方から踏み出すチャンスを与えられた。いまたいへん心待ちにしているのは、東京や東京以外の場所で出会った4名のアーティストがワルシャワを訪れることだ。ポーランドにはたくさんの仕事があることを確信して私は彼らを招待したのだ。森弘治氏はワルシャワでの活動をいますぐにでも始めることだろう。舞台でもリハーサルでも私は彼の作品に文字通り、そして比喩的な意味でも心を打たれた。彼は駆け出しの俳優たちに日常的な言葉で社会的な役割を与えたのだった。森氏はまたアーティスツ・ギルドの共同創設者兼ディレクターでもある。アーティスツ・ギルドはビデオやフィルム機材をアーティストが使用、共有できるようにした素晴らしいグループである。このようにして外部からの資金援助に頼らず、徐々に独立できるように活動している。
しかし機材に対するニーズの問題を技術的に解決することは、アーティストが自分の作品を自分で管理することを検討する第一歩に過ぎないようであり、この分野におけるポーランドの事例に直接触れることが森氏のレジデンシー・プログラムの重要なテーマのひとつになるだろう。そして1年後にはすべての必要な資金が獲得できることを私たちは願っている。またウジャドゥスキー城現代美術センターとワルシャワの中心にある牧歌的な公園がHyslom(ヒスロム)の活動によりどのように変わるのかをみるのも楽しみだ。Hyslomは建築家を含む三人のアーティスト集団で、直観、好奇心、精密な行動を取り入れることにより、地域を限定的で単一的な支配から解放し、発見、儀式、そして自由なエネルギーの場に変えるのである。スケートボードのようなパワー、そして泥のなかのダンスのようなパワーである。さあ、いまから取り掛かろう!
★1──ガル・キルム(Gal Kirn)「レジデント・アーティストが来る、スペースをつくろう(Artist in Residence Coming, Make Some Space)」。
URL=http://re-tooling-residencies.org/resources/research/artist-in-residence-coming-make-some-space-by-gal-kirn(検索日=2014年2月18日)
★2──パスカル・ギーレン(Pascal Gielen)『アート集団のつぶやき、グローバルアート、記憶とポスト・フォーディズム(The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Memory and Post-Fordism)』(ヴァリズ、アムステルダム、2009)。
文化庁へ戻る
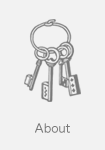




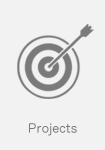






![[購読申込]](../../../img/subscribe.gif)
![[購読解除]](../../../img/unsubscribe.gif)


